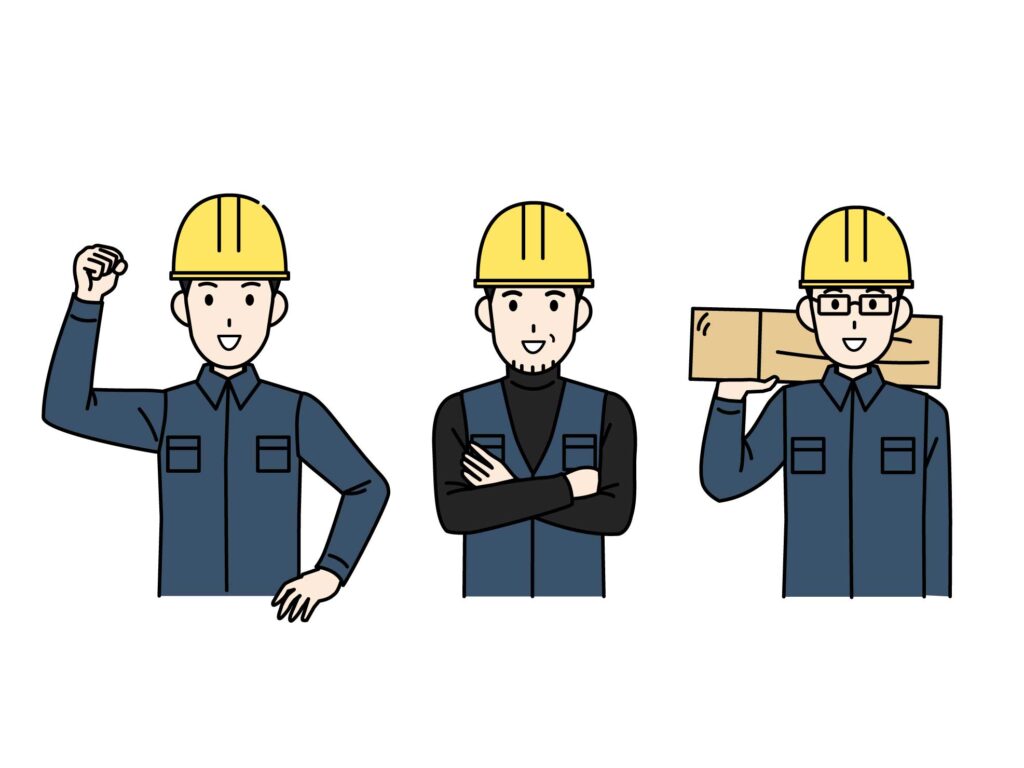
「職人は稼げる」と言う人もいれば、「職人は稼げない」と言う人もいます。
果たして稼げるのか?稼げないのか?
意見が分かれるのはどういう事なのでしょうか?
本当のところ職人はどのくらいの稼ぎ、収入になるのか、これから職人を目指そうと考えている人、現役の職人で自分の稼ぎを増やしたいと考えている人、私自身や回りにいる職人(建設・建築)の方々を例に解説します。
後述の例よりもっと多く稼いでいる職人もいますが、それは会社員でも同じです。
出来る人間は職人だろうと会社員だろうと高収入ですので、平均的なところで説明したいと思います。
| 種類 | 収入 | 月/22日稼働 | 月/25日稼働 | 月22日稼働/年収 |
| 職人見習い | 人工・日当8000円~10000円程度 | 17.6万~22万 | 20万~25万 | 221.2万~264万 |
| 職人(日当) | 人工・日当10000円~25000円程度 | 22万~55万 | 25万~62.5万 | 264万~660万 |
| 職人(1人親方) | 人工・日当25000円~50000円程度 | 55万~110万 | 62.5万~125万 | 660万~1320万 |
上記を見て高いか安いか、如何でしょうか?
会社員は週休2日制のところが大半ですので、職人も同じく週休2日制(現実は週休1日が多い)に揃えて比較してみます。
某サイト情報によると、会社員の平均年収は449万円、職人の平均年収は420万だそうです。
日当で働く職人の264万~660万の中間をとると462万となります。
しかし、一方で1000万以上稼いでいる職人も多数います。
それも30代位の年齢でも珍しくありません。
会社員の場合、1000万円に到達するのは50代以上の年齢になってからが大半ではないでしょうか。
ここまでの説明だと職人が稼げそうに見えますが、現実は違います。
| 職人 | 会社員 | |
| 健康保険 | 自己負担 | 会社と従業員で折半 |
| 国民年金 (会社員は厚生年金) | 自己負担 | 会社と従業員で折半 |
| 労災保険 | 自己負担(加入は任意) | 会社負担 |
| 交通費 (ガソリン・電車代等) | 自己負担 (元請会社側負担の場合もあり) | 会社負担 |
| 作業服・スーツ | 自己負担(消耗度激しい) | 自己負担 |
| 工具・備品 | 原則自己負担 | 会社負担 |
| 作業車両費・維持費 | 自己負担 | 会社負担 |
職人の多くは個人事業主です。
会社員は健康保険・厚生年金の支払いの半分を会社が負担してくれますが、職人の場合、健康保険・国民年金の費用は全額自己負担となり、国民年金だと負担額は安いですが、将来的にもらう年金額も安くなります。
また、会社員であれば労災保険は全額会社負担、個人事業主の職人は自己負担となります。
その他にも自己負担しなければならない経費は多々あります。
職人との会話の中で語られる「月100万円稼いだ」は売上高であって収入ではありません。
職人は毎月の売上も一定ではなく、経費もどのくらい掛かったか、確定申告の時期でもない限り把握していないことが多いので、売上高を自分の稼ぎとして語られているのです。
個人事業主の一人親方の職人が、法人化し社会保険等に加入して、売上から各種経費を差し引いた場合、給料として自分自身支払える額は3割~5割程度は目減りします。
年収500万円~700万円程度
建築現場の多くは未だに週休1日で動いている場合が大半ですので、会社員よりも40~50日多く働いていることも忘れてはいけません。
| 職人 | 60~75日程度(月4日+お盆、正月、GW) |
| 会社員 | 105日~120日(法定最低休日105日) |
年収500万円~700万円は悪くないように思えるかもしれませんが、休日の数は大きな差があります。
もし同じだけ休日を取るとするとどうでしょうか。
| 職種 | 年収 | 年間休日 | 年間稼働日数 | 日収 |
| 職人(法人一人親方) | 500万円 | 60日 | 305日 | 16,393円 |
| 会社員 | 500万円 | 105日 | 260日 | 19,230円 |
年齢を重ねて体力が落ちてくると、若いころと同じ様に働くことは難しくなってきます。
上記の日収16,393円の職人が、年間休日105日=稼働日数260日で働いた場合、年収426万円(千円以下切捨て)となります。
以上の事を踏まえてみて如何でしょうか?
それぞれ感じ方は異なるでしょうが、私は職人は稼げないと感じています。
職人は自分の手を動かすことで稼ぎを生み出しているので、熟練して仕事が早くなるといっても限度があります。
職人が、純粋な職人(施工者)として稼ぎを増やすのは難しいですが、職人としての仕事以外に付随、関連した仕事をこなせるようになると、手仕事の限界以上に稼げるようになってきます。
それについてはまた後日、別記事にて記述いたします。


